“ほぼ寝っ転がるだけ”のワークショップ!駒沢で頑張る女性の体を「ゆるめる」。<しみん先生>
- こもれびスタジオ
- しみん先生



1882(明治15)年の開校から142年、仏教の教えと禅の精神をもとに設立された駒澤大学。その長い歴史の中で2021年4月、初の女性学長に就任し、新たな風を吹き込んできた各務洋子先生(グローバル・メディア・スタディーズ学部教授)です。学長として駆け抜けた4年間も任期の終わり。これまでの取り組みや未来への思いを語っていただくために、駒澤大学の卒業生でもあるこもれび記者·MIKAKOがインタビューにいきました。撮影は駒澤大学2年生·森山蒼斗さんです。
ーー女性の学長就任は、駒澤大学では初めてのことだったのですよね?
そうなんです。駒澤大学の長い歴史の中で、女性学長はいませんでした。日本の大学は、女性学長の数が世界の大学に比べて少ないのが現状ですが、少しずつ変わってきています。
ーー大学の学長選とはどのように行われるのですか
駒澤大学の学長は、勤務する専任教職員による学長候補者選挙によって、最終学長候補者を決定し、理事会の議を経て理事長が任命するという仕組みで決まります。任期は4年。私の学長就任は2021年4月でした。
就任当初、私立大学における女性学長の割合は日本全国で11%未満、この4年間で13%に増えました。日本のジェンダーギャップ指数も146ヵ国中125位(2020年)から118位(2024年)に上がりましたがまだまだ改善の余地はありますね。

――学長として、普段はどのようなことをされていますか?
駒澤大学は7学部17学科、大学院には9研究科・15専攻(法科大学院含む)があります。サークル·部活動も多く、入試や授業関連の業務から学生生活まで、さまざまな分野で決めなければならないことがあり、会議の数は多いです。地元世田谷区に属する大学が集まる会合や、仏教系大学、東京都の大学、日本の私立大学の集まりもあり、忙しく動いています。
ーーそのような中、4年間の任期でどのようなことを目指していたのですか?
私が学長になる時に掲げた公約は、『デジタル化』と『ダイバーシティ』です。正確に言えば、『デジタル化の推進による大学のマネジメント改革』と『ダイバーシティの尊重による個を活かす大学』という2本柱。
もう少し詳しくお願いしますーー
駒澤大学の歴史は433年ととても長いです(前身である曹洞宗の「学林」ー曹洞宗が禅の実践と仏教の研究、漢学の振興を目的として設立した教育機関ーを含め)。時間の経過とともに積み重ねてきた歴史と伝統こそがオリジナリティ。その駒澤大学らしさを「今」に伝えることが、私の使命。大学の個性をいかに、世の中に知っていただけるか、そのためにはどうしたら良いかを考えてきました。
インターネットが出現して以来、大学内でも働き方が変わり、キャンパスでは学び方に変革が起きています。例えば、駒大のもつ仏教や禅に関する書物は、世界中の研究者から需要が高く、デジタル化により世界のどこからでもアクセスが可能となりました。技術は刻々と変わり続けますが、大学の現場においてはまだまだです。常に先端のデジタルツールが使えるようになっていることが理想です。

ーー大学はデジタル化に関して消極的だったということですか。
残念ながら。大学だけでなく日本全体が遅れていると言われています。毎年、スイスの国際経営開発研究所(IMD)が世界デジタル競争力ランキングを発表していますが、日本は前年の(2024年)調査から1つ順位を上げたとはいえ、31位。
*順位は、世界67カ国・地域を対象に、毎年、実施する調査をもとに発表されますが、政府や企業、社会の変革につながるデジタル技術を導入・活用する能力について、①知識(人材や教育・訓練)、②技術(規制枠組み、技術的枠組み)③将来への準備(DXに対する社会の準備度合い)など59の評価基準で分析され、評価が出されています。
こうした評価が全てではないのですが、デジタル化が遅れていることで困るのは社会に出ていく学生たちです。卒業式の1週間後には、様々な組織でそれぞれに仕事を始めることになります。その時に、スムーズに仕事に着手できるように、手段としてのツールは、常に最先端に触れる環境を提供したいというのが私の願いです。
すでに授業支援ツールは、学生や教員の授業運営に役立つものが備えられています。授業中に質問をチャット機能で送信しておき、教員がその場で答え、授業が思わぬ展開に進むといった進め方も可能になりました。この新しいツールに対応していくためには、指導する側が研修を受ける必要があります。技術革新が進めば進むほど、人材への投資が必要となります。
――4年間で、組織に変化は見えてきましたか?
少しずつですが変化してきていると思います。私が学長になった当初はちょうどコロナ禍の真っ只中。大変なことも多かったですが、その一方でデジタル化が一気に進みました。これはハンディキャップをもつ学生さんから聞いた話ですが、以前は車椅子で通学する場合、ラッシュアワーを避けるために1限目の授業に出席できず、卒業するための単位の取得が比較的難しい局面が多々あったようです。しかし、オンライン授業が導入されたことで、従来より卒業に必要な単位をスムーズに取得することができるようになったと聞きました。これまで不可能だったことが可能になったという話は非常に勇気づけられます。

ーー学長の任期は2025年3月末までですが、現在(取材は2024年11月に実施)の心境はいかがですか?
3月末日まで、全力で任期を全うしたいと考えています。とにかく、会議などで穴を開けないように細心の注意を払ってきたつもりですが、4年の間には体調を崩してしまったり、転倒して足の骨を折ったりと想定外のことが起き、迷惑をかけたこともありました。いまは、最後の一日まで、気を引き締めて貫徹したいという気持ちだけです。
――駒沢エリアに大学が位置するメリットには、どんなことがあると思いますか?
駒澤大学でも、地域の方々が参加できる公開講座や日曜講座や夏祭りを開催していますし、学食にも足を運んでいただけます。大学構内の博物館や図書館などで行う定期的なイベントや活動を、もっと地域の方々に積極的にアピールしていきたいと思っています。大学は地域の方々と共に存在しています。
――大学は学生にとってどのような場所でありたいと思いますか?
日本は人口減少が加速していますが、世界は増加し続けています。もはや日本人だけ、日本語だけでは通用しない時代。年齢やバックグラウンドに多様性があると学びの幅も広がります。できるだけ色々な人が混ざり合う“ごちゃまぜ”の環境の中で、共通の課題に共に取り組むことが大切です。
留学生やハンディキャップを持つ学生、異なる年代の学生が一緒に学べば意見がまとまらないこともあります。実はそれがとても大事なことで、大学時代に大変な思いを存分にしておけば、社会に出たときに『このくらい大したことないな』と感じられるようになるでしょう。大学は少しぐらい大変で、難題を乗り越える経験ができる場所であってほしいと思います。
――具体的なエピソードはありますか?
駒澤大学にコメディアンとして活躍されている欽ちゃん(萩本欽一さん)が入学された時のことは印象深いです。欽ちゃんは第二外国語でドイツ語を履修され、若い学生さんの2倍くらい時間をかけたと聞きました。一方で仏教哲学の授業では欽ちゃんが自身の経験を活かしてイキイキと話す。お話も面白いし、人生の先輩の言葉を聞くことで、若い学生たちが新たな視点を学ぶ機会になったとのことです。
社会に出ると、同じ年代の人とだけ働くことなどほとんどないです。異なる年代やバックグラウンドの人と接する機会が大学時代にあると、それが社会に出たときに大いに役立ちます。
ーー各務学長は子育てをしながら留学をしていたと聞きましたが?
あの時は大変でした。子どもが1歳の時に、スイスのビジネススクールに留学した夫に同行。途中で、私にも留学する機会が訪れ、国際ロータリークラブの全額支給奨学生となりました。指定された留学先がなんとアリゾナ州立大学のビジネススクール。両親をはじめ周囲に相談しましたが、賛成してくれたのは夫とその友人一人でした。「まずは行ってみて、だめだったら帰ってくれば良い」と夫と話しました。子どもを連れてスイスからアリゾナに、決死の覚悟で行ってみたところ、大学の正門前にプリスクールがあり、何人もの学生が子どもを預けながら大学に通っていました。子連れの留学は特別なことではなく、人生の選択肢の一つにすでに入っていたのです。
現地に着いた瞬間、愕然としましたが、「世界は広い」また、「道は開ける」ということが現実として目の前に広がりました。

ーーそこまで頑張れたのはどうしてですか?
これまでの経験を活かして、生涯、社会に貢献していきたいという思いがあり、貢献するためには、自分自身の実力をもっと高めたいという、それが原動力だったと思います。
ーー先生ご自身はこれからをどのように考えていますか?
再び、いち教員に戻ることができて幸せですし、とても楽しみでもあります。
4年間の学長の経験で気付いたことを授業で活かしたいと思っています。また研究活動にも新たな広がりが出てきそうですので、研究生活に戻れることにも幸せを感じています。
ーー具体的にはどんなことを考えていますが?
私の専門は経営学ですので、専門の教育と研究に戻ります。この4年間で格段に変革が起きている外部環境の中で、様々な組織がそれぞれに活動を続けています。例えば、人口減少は人手不足に直結します。日本は少子化が課題である一方で、人口増加の国々が目立ってきました。AI技術の進展も経営には必須の検討課題です。特に、海外の方々と共に仕事をすることが当たり前のいま、最大の課題は何なのか、それを解決するにはどうすれば良いのかなど、当事者意識をもって真剣に考えなければなりません。そのためには、異なる価値観をもつ人達と共に働くために必要なことは何か、どうすればそれぞれの目標を達成することができるのか。私の専門ではダイバーシティマネジメントの領域がとても大事になります。国や文化の違いだけではなく、年齢、価値観、生き方の違いに至るまで、多様な個性をもつ仲間とより良く協働するための方策を考えたいと思っています。
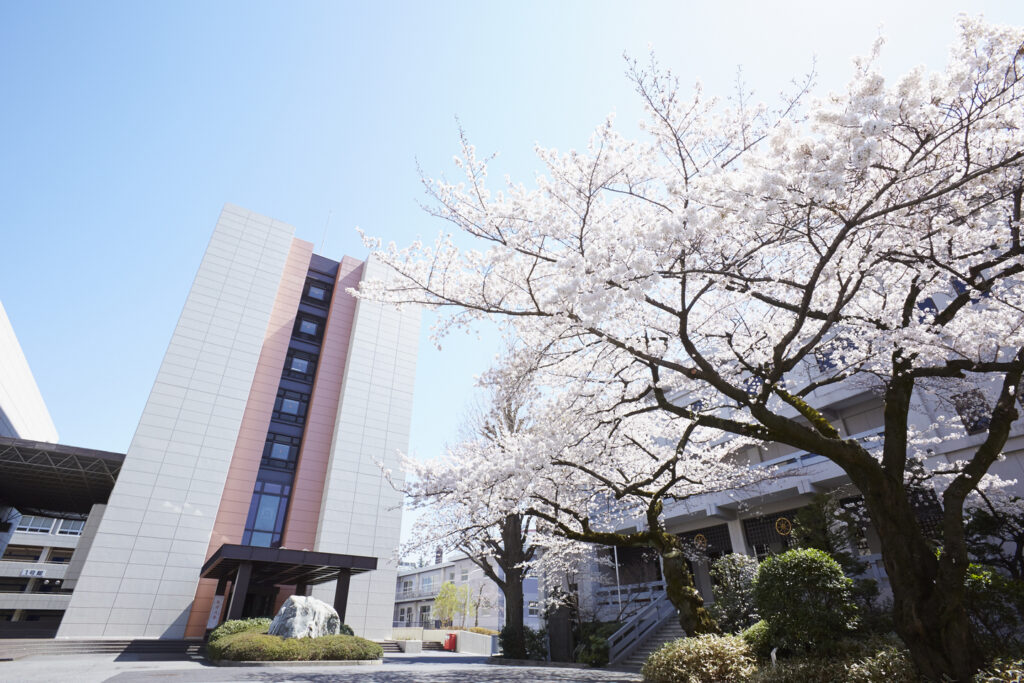

駒澤大学グローバルメディアスタディーズ学部卒。化粧品会社へ就職。
専業主婦となり2歳差ワンオペ育児に奮闘。
コロナ渦での起業を経て、3人目の出産と同時に地域・社会貢献活動へシフト。
2匹の犬と料理とスポーツが好き。推しは夫。
夫が駒沢でオープンしたコーヒーショップcoffee&dogsも手伝う。